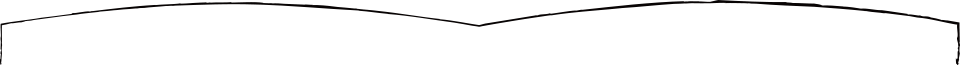音の先にあるもの
-阿久比を歩く。まちを見つめる-
「ガシャーン、ガシャーン、ガシャーン」
日常にはいろいろな音が溢れている。繰り返される音、1回きりの音、歌のような音、心地の良い音、嫌な音。日々繰り返される変わらない日常の、変わっていく気のない緩やかなリズムがそこにはある。
住宅街のなだらかな上り坂をゆっくり進むと、かすかに機械の音が聞こえる。昼下がりの光の中、赤や黄色に色づいた落ち葉の甘い香りとともにその音はだんだんと近づいてきた。
三角が連なるノコギリ屋根が印象的な綿の織物工場が1950年代には70軒ほどあったという知多郡阿久比町。阿久比の象徴だったともいえるノコギリ屋根の工場は今は2軒だけ稼働している。ほとんどが閉鎖されるとともにいつの間にか駐車場やマンションなどに変わりまちの景観を失ってしまったという。それでも残っている2軒の木綿工場からは今日も「ガシャーン、ガシャーン、ガシャーン」という旧式シャトル織機*の音がリズミカルに漏れ出し、まちの風景と一体となっている。
* 織物の経糸に緯糸を通す際にシャトルと呼ばれる器具を使って糸を互い違いに通していく構造の織機。

四季のうつろいを楽しめそうな緑に囲まれた小道
このまちにはもうひとつのリズムがある。山と谷が多く、起伏に沿ったり横切ったりしてつながれた、曲がりくねった細い道がリズミカルにゆきかっている。人ひとり通れるくらいの小道は、きっとその辺りに住む人々が日常生活で使うもの。公道だけど私道みたいな、もしかしたら誰かの道だけど、“ご自由にどうぞ”的に使われている道もあるのかもしれない。そういったほど良いつながりがこのまちには多い気がする。家と家との間にあったり、竹林の中を進む道だったり。この道はいったいなんのためにつくられたのかと首をかしげたくなるものもあって面白い。どれも見通しや風景、自然との調和が考えられているし、人と人との距離がとても近いと感じた。前から歩いてくる人とすれ違うときに思わず「こんにちは」と言ってしまう距離感が心地良い。
石や竹、植物を使った垣根、板張りの家、ツル植物のアーチ、緑に囲まれた石段がある路地。ここには昔からの自然素材が当たり前のように存在している。絶妙なサイズ感や陽の当たりぐあい、周囲の建物とのつながりもあり、もともとある自然へのまなざしを感じた。一つひとつの音がリズムをもって音楽となっていくように、一つひとつの要素がこつこつと積み重なって、全体としての空間ができあがりまちになっていく。そこにある抑揚が調和したときにそのまちの美しさが見えてくる。ただ歩いているだけで楽しいと感じることができるのは、先人が積み上げてきた配慮が美しさの基準となって今も残っているからだろう。
そんなことを考えながら歩いていると、ここにも、あそこにも!と、このまちらしい建物や風景に気がつく。その「らしさ」を拾い集めてみると「のどか」とか「のんびり」という言葉が浮かんでくる。それぞれの時代を経てきた中で、このまちが変わったこと、変わろうとせずに大切にしていること。その周縁で、ふんわりとした言葉だけでは言い表せない、なにかいとおしさのようなものを感じた。

夕陽を背にするとススキが幻想的にキラキラと輝く
それにしても、あの連続する「ガシャーン、ガシャーン、ガシャーン」という音のリズムが町内70ヵ所から溢れ出る日常とはいったいどのようなものだったのだろう。音が体に棲みついて、次第にそこに暮らす人々の一部になっていったのではないだろうか。
言葉が人間を形成しているという話を聞いたことがある。同じ人でも日本語で話しているときと英語のときとでは性格が変わってくるらしい。それであれば音のリズムも同じであろう。旧式シャトル織機について、知多木綿のカタログに「現代の織機に対して約10-20分の1と低速で」織ると書かれていた。1本のシャトルが行ったり来たりしながら織り上げる構造の旧式シャトル織機は、時代が変わって技術が向上したからといってスピードが上がるわけではない。現代の暮らしの20分の1のテンポ。そのリズムが半世紀以上もこのまちで紡ぎ出されていること。それがのんびりをつないできた「阿久比らしさ」の根っこになっているのかもしれない。

旧式シャトル織機で織った生地はふっくら優しい肌触り
私たちはまちを見つめるとき、どうしても表面的なところに意識が向いてしまうのだと思う。ナントカという施設があって面白いとか、おしゃれにデザインされたお店がたくさんあるとか。モノを見るときもデザインや材質、目に見える外側の部分を見てわかったような気になっている。一度頭を空にして、まちと出会い直すのが良いのかもしれない。まっさらな気持ちで身近に起こる小さなモノやコトに目を向け、耳を澄ましてみるとまったく違うまちの見方があることに気がつく。
阿久比のまちを歩いてみたら自分が暮らすまちの「らしさ」を見つけてみたいと思うようになった。見慣れた景色、聞き慣れた音、そういう当たり前の日常の中に実は大切なことがあったりするのだろう。我がごとになると急に立ち止まってしまうけれど、まとわりついて離れない先入観や感情たちに振り回されながら私は右往左往してみようと思う。
写真/太田美佳